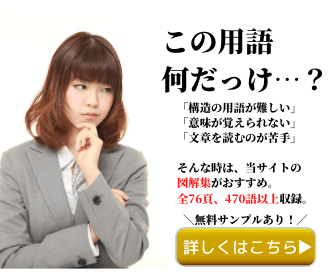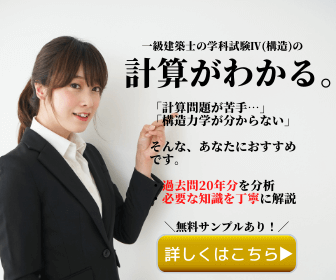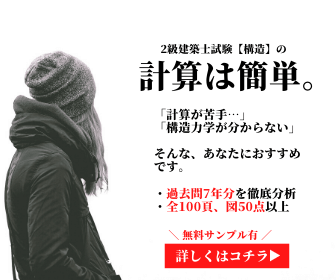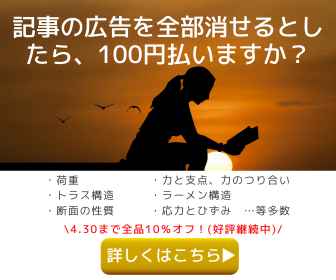横補剛材間隔と必要本数の計算
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)
横補剛材とは、大梁の横座屈を防止(横補剛)するための部材です。横補剛材は横補剛の目的のみで設置する場合もありますが、
床荷重を受けて大梁と接合する小梁を横補剛材と兼ねて使うこともあります。大梁に対して横補剛材を何本配置するかは
「はりの全長にわたって均等配置する方法」または「はりの端部に配置する方法」の2つがあります。
今回は、横補剛材の一般的な配置方法である「はりの全長にわたって均等配置する方法」について説明します。さて、横補剛材を均等配置する検討式は下記の通りです。
①はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合
λy ≦λ=170 + 20n(400ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
λy ≦λ=130 + 20n(490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
λy =L/iy
横補剛材を等間隔に割り付けるとき、横補剛数は上式で求めることができました。しかし、「等間隔に~」という部分も重要で、
たとえ補剛材の数が揃っていても、間隔にバラつきがあったとき、それは横補剛間隔を満足しているとは言えません。
横補剛の必要本数をnと仮定します。このとき、先ほど明記した式から横補剛材間隔を求めましょう。
400級の鋼材を用いるとき、その必要間隔は、
Lb=iy×(170+20×n)÷(n+1)
で求めることができます。iyは断面二次半径です。490鋼材を用いるときは、170を130に変更して計算します。
分母で梁長さを逆算し、分子で横補剛の必要本数nが入ったときの床面数を表しています。
Lbを超えたスパンにはできないので、そもそも横補剛材が均等間隔に配置できない場合は注意が必要です。
②主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
lbmax = min( 250・(Af/h) , 65・iy )(400ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
lbmax = min( 200・(Af/h) , 50・iy )(490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
共通してiyは弱軸回りの断面二次半径を表しています。
つまり、横座屈という現象は荷重方向に対しては面外、弱軸方向にはらみ出すような現象なので、弱軸回りの断面二次半径が必要なのです
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)
▼スポンサーリンク▼
▼用語の意味知らなくて大丈夫?▼
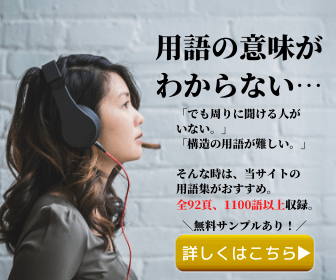
▼同じカテゴリの記事一覧▼
- 座屈応力とは?1分でわかる意味、降伏応力との関係、オイラー座屈荷重との違い、単位
- 片持ち柱の座屈荷重の計算式と導出方法
- 片側ピン・片側固定柱の座屈荷重の計算式と導出方法
- 両端固定柱の座屈荷重の計算式と導出方法
- 境界条件による座屈長さの違いについて
- 横補剛材とは何?検討方法と必要本数は?
- 横補鋼材としての方杖
▼カテゴリ一覧▼
- 建築物と構造力学の関係(まずは、苦手な勉強の進め方から)
- モデル化を学ぶ(まずは、構造物のモデル化から)
- 静定構造物の解き方を学ぶ(まずは、静定構造物に関する基礎用語から)
- 断面の性質を学ぶ(まずは、断面図形に関する基礎用語から)
- 梁のたわみを学ぶ(まずは、梁のたわみと基礎用語から)
▼他の勉強がしたい方はこちら▼
更新情報
- 当サイトでは、ほぼ毎日、記事更新・追加を行っております。
- 更新情報として、先月分の新着記事を一覧表示しております。下記をご確認ください。
- 新着記事一覧
プロフィール

- 略歴▼
- 名前 ハナダユキヒロ/MITUME lab代表.
- 2010年 弊サイトを開設
- 2010~2017年 国立大学大学院修了
- 2017年12月に当HPが書籍化。
- 「わかる構造力学」
- 2022年4月に「わかる構造力学」の改訂版出版。
- 「わかる構造力学(改訂版)」
- 10数年以上、建築の学問、研究、構造設計の実務に携わった経験を元に、未経験の方、建築関係の学生、社会人の方に役立つ知識を、分かりやすくお伝えします。
- 当サイトの目的▼
- 建築学生が学ぶ「構造力学」の目的
- とりあえず10記事▼
- 初めましての方に10記事用意しました
- おすすめ書籍紹介▼
- ハナダユキヒロが建築関連書籍の良書を選びました
同じカテゴリの記事一覧
- HOME > 構造力学の基礎 > 横補剛材間隔と必要本数の計算
- 1級の過去問(計算)解説
- 限定メルマガ
- わかる建築構造の用語集・図解集
- 1頁10円!PDF版の学習記事