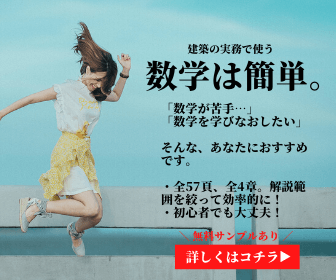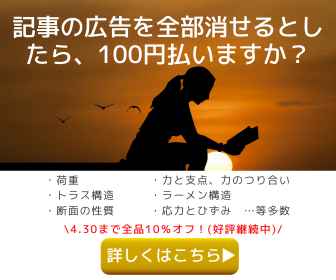分配法則とは?1分でわかる意味、四角形の面積、計算、順番
管理人おすすめ書籍⇒ 増補改訂版 中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる [ 小杉 拓也 ]
分配法則(ぶんぱいほうそく)とは、a(b+c)=ab+acを満たす法則です。また、a(b+c)を(b+c)aに入れ替えても分配法則は成り立ちます。今回は分配法則の意味、四角形の面積、計算、計算の順番について説明します。
管理人おすすめ書籍⇒ 見るだけで理解が加速する 得点アップ 数学公式図鑑 [ あきとんとん ]
分配法則とは?
分配法則(ぶんぱいほうそく)とは、
a(b+c)=ab+ac
(b+c)a=ab+ac
が成り立つ法則です。数学では欠かすことのできない法則です。是非覚えてくださいね。なお、a(b+c)はa×(b+c)を意味します。「×」は省略することが多いです。
分配法則と四角形の面積
分配法則がなぜ成立するか、四角形の面積を使って説明します。分配法則の証明でよく用いる方法です。下図をみてください。縦の長さa、横の長さbとcの四角形があります。
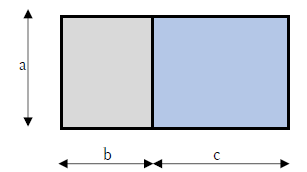
四角形のそれぞれの面積は、
面積1=ab
面積2=ac
です。面積1+面積2を計算すると
面積1+面積2=ab+ac
です。次に考え方を変えて、縦の長さa、横の長さが(b+c)の四角形として面積を計算します。
面積1+面積2=a×(b+c)=a(b+c)
ですね。計算方法は違いますが、面積の結果は同じになります。よって、
a(b+c)=ab+ac
です。また四角形の面積は、「縦×横」=「横×縦」でも結果は同じです。下記のように横と縦の長さを入れ替えて計算しても、結果に変わりないですね。
(b+c)a=ab+ac
分配法則の計算
分配法則を用いて、下記の問題を解きましょう。
5×(5+3)
簡単ですね。
5×(5+3)
=5×5+5×3
=25+15=40
次の問題です。
(8+3)×5
=8×5+3×5
=40+15=55
分配法則と順番
分配法則は、前述したように順番は関係ないです。
a(b+c)=ab+ac
(b+c)a=ab+ac
四角形の面積は、縦と横のどちらを掛けても結果は同じになりますね。
管理人おすすめ書籍⇒ 見るだけで理解が加速する 得点アップ 数学公式図鑑 [ あきとんとん ]
まとめ
今回は分配法則について説明しました。意味が理解頂けたと思います。分配法則は、a(b+c)=ab+acとなる法則です。数学の問題を解くために必須の知識です。是非理解してください。また、分配法則の証明として、四角形の面積の関係を解説しました。数式だけでなく、図形のイメージを持つと良く理解できます。下記も参考になります。
交換法則とは?1分でわかる意味、読み方、計算、減法と除法、分配法則との関係
結合法則とは?1分でわかる意味、読み方、式と計算、分配法則、除法との関係
管理人おすすめ書籍⇒ 増補改訂版 中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる [ 小杉 拓也 ]
▼スポンサーリンク▼
▼同じカテゴリの記事一覧▼
- 等号とは?1分でわかる意味、読み方、種類、不等号との違い
- 右辺とは?1分でわかる意味、左辺、両辺、移項との関係
- 左辺とは?1分でわかる意味、右辺と両辺との違い、移項との関係
- 両辺とは?1分でわかる意味、両辺の二乗、両辺を割る、分数との関係
- 等式とは?1分でわかる意味、記号と等号、種類、不等式との違い
- 恒等式とは?1分でわかる意味、読み方、方程式との違い、見分け方
- 方程式とは?1分でわかる意味、移項、1次方程式の解き方と計算問題、分数の関係
- 交換法則とは?1分でわかる意味、読み方、計算、減法と除法、分配法則との関係
- 結合法則とは?1分でわかる意味、読み方、式と計算、分配法則、除法との関係
- 2次方程式とは?1分でわかる意味、解き方、解の公式、因数分解との関係
- 連立方程式とは?1分でわかる意味、問題の解き方、加減法と代入法
- 不等式とは?1分でわかる意味、計算と解き方、問題、不等式の性質
- 1次不等式とは?1分でわかる意味、マイナス、ルート、問題、符号との関係
- 連立不等式とは?1分でわかる意味、解と問題の解き方
▼カテゴリ一覧▼
- 建築物と構造力学の関係(まずは、苦手な勉強の進め方から)
- モデル化を学ぶ(まずは、構造物のモデル化から)
- 静定構造物の解き方を学ぶ(まずは、静定構造物に関する基礎用語から)
- 断面の性質を学ぶ(まずは、断面図形に関する基礎用語から)
- 梁のたわみを学ぶ(まずは、梁のたわみと基礎用語から)
▼他の勉強がしたい方はこちら▼
更新情報
- 当サイトでは、ほぼ毎日、記事更新・追加を行っております。
- 更新情報として、先月分の新着記事を一覧表示しております。下記をご確認ください。
- 新着記事一覧
プロフィール

- 略歴▼
- 名前 ハナダユキヒロ/MITUME lab代表.
- 2010年 弊サイトを開設
- 2010~2017年 国立大学大学院修了
- 2017年12月に当HPが書籍化。
- 「わかる構造力学」
- 2022年4月に「わかる構造力学」の改訂版出版。
- 「わかる構造力学(改訂版)」
- 10数年以上、建築の学問、研究、構造設計の実務に携わった経験を元に、未経験の方、建築関係の学生、社会人の方に役立つ知識を、分かりやすくお伝えします。
- 当サイトの目的▼
- 建築学生が学ぶ「構造力学」の目的
- とりあえず10記事▼
- 初めましての方に10記事用意しました
- おすすめ書籍紹介▼
- ハナダユキヒロが建築関連書籍の良書を選びました
同じカテゴリの記事一覧
- 等号とは?1分でわかる意味、読み方、種類、不等号との違い
- 右辺とは?1分でわかる意味、左辺、両辺、移項との関係
- 左辺とは?1分でわかる意味、右辺と両辺との違い、移項との関係
- 両辺とは?1分でわかる意味、両辺の二乗、両辺を割る、分数との関係
- 等式とは?1分でわかる意味、記号と等号、種類、不等式との違い
- 恒等式とは?1分でわかる意味、読み方、方程式との違い、見分け方
- 方程式とは?1分でわかる意味、移項、1次方程式の解き方と計算問題、分数の関係
- 交換法則とは?1分でわかる意味、読み方、計算、減法と除法、分配法則との関係
- 結合法則とは?1分でわかる意味、読み方、式と計算、分配法則、除法との関係
- 2次方程式とは?1分でわかる意味、解き方、解の公式、因数分解との関係
- 連立方程式とは?1分でわかる意味、問題の解き方、加減法と代入法
- 不等式とは?1分でわかる意味、計算と解き方、問題、不等式の性質
- 1次不等式とは?1分でわかる意味、マイナス、ルート、問題、符号との関係
- 連立不等式とは?1分でわかる意味、解と問題の解き方
- HOME > 数学の基礎 >分配法則とは?1分でわかる意味、四角形の面積、計算、順番
- 1級の過去問(計算)解説
- 限定メルマガ
- わかる建築構造の用語集・図解集
- 1頁10円!PDF版の学習記事