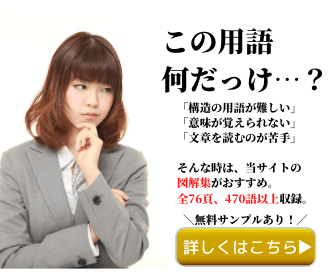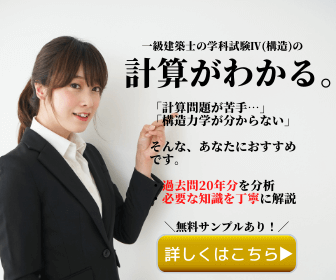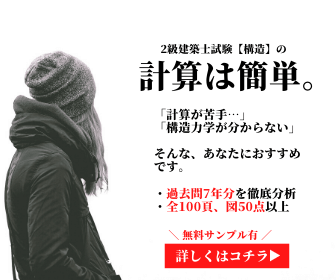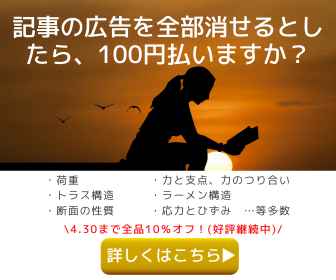- HOME > 鉄筋コンクリート造の基礎 > ワーカビリティとは?1分でわかる意味、スランプ、AE減水剤との関係
ワーカビリティとは?1分でわかる意味、スランプ、AE減水剤との関係
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)
ワーカビリティをご存じでしょうか。コンクリートの施工性に関する用語です。今回は、ワーカビリティの意味や、スランプとの関係を説明します。
※スランプの意味は下記が参考になります。
スランプフローとは?1分でわかる意味、スランプとの違い、測定方法
スランプ試験ってなに?スランプコーンとスランプ値、Fcとの関係
ワーカビリティってなに?
ワーカビリティは、コンクリートを型枠に打ち込むときの施工のやり易さ、です。「ワーカビリティが良いコンクリート」とは、コンクリートの施工性が良いと同義です。
さて、ワーカビリティは、JASS5で下記のように定義されています。※JASS 5については下記が参考になります。
「コンクリートのワーカビリティは、打ち込み箇所および打ち込み・締固め方法に応じて、型枠内および鉄筋周囲に密実に打ち込むことができ、かつブリーディングおよび材料分離が少ないものとする。」
と書いてあります。
※コンクリートの打ち込み、締固めは下記が参考になります。
コンクリートの打ち込みとは?1分でわかる意味、高さ、打ち込み時間
コンクリートの締固めとは?1分でわかる意味、留意点、機械、間隔
つまり、ワーカビリティは単に施工がやり易いだけではダメです。過去の建築物の中には、生コンクリートに水を混ぜて、現場で施工を行いやすくしていました。
水のようにサラサラの液体と、生クリームのように原型を留める半固体で、型枠に隅々まで行き届かせるなら、断然「サラサラの液体」がやり易いですね。
しかしこれは言語道断で、コンクリートの強度が落ちるばかりか、劣化もすぐに進行します。
よってワーカビリティは、ブリーディングや材料分離が少なくすることも必要です。
100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事
ワーカビリティとスランプの関係
ブリーディングや材料分離を判断する指標の1つがスランプ値です。※スランプ値は下記が参考になります。
コンクリートのスランプ値は?1分でわかる意味と規定、スランプ値、18cm
スランプ試験ってなに?スランプコーンとスランプ値、Fcとの関係
スランプが大きいと、材料分離やブリーディング量が大きくなります。
逆にスランプ値が少ないと、前述した問題は起きにくいですが、ワーカビリティは悪くなります。
ワーカビリティとスランプ値の双方を兼ねたコンクリートが必要です。
現在、スランプ値は18cm以下が基本です。ブリーディング量に関しては、JASS5にも評価基準がまとまっていないのが現状です。
ワーカビリティを変えるAE減水剤
ワーカビリティはスランプ値との兼ね合いだと説明しました。昔は水量を増やして(セメント量を減らして)、ワーカビリティを良くしていました。現在では高性能AE減水剤という、水量を減らしてもワーカビリティが損なわれない混和材があります。
※高性能AE減水剤に関しては下記が参考になります。
まとめ
今回はワーカビリティについて説明しました。ワーカビリティの意味自体は簡単です。
しかし大切なのは、ワーカビリティとスランプの関係です。下記も併せて参考にしてください。
コンクリートのスランプ値は?1分でわかる意味と規定、スランプ値、18cm
スランプ試験ってなに?スランプコーンとスランプ値、Fcとの関係
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)
▼スポンサーリンク▼
▼用語の意味知らなくて大丈夫?▼
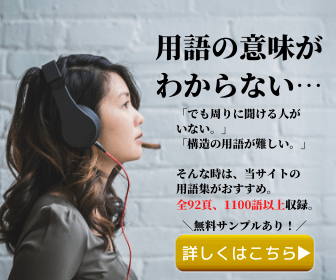
▼同じカテゴリの記事一覧▼
- 富配合とは?1分でわかる意味、読み方、貧配合との違い、杭との関係
- フレッシュコンクリートとは?1分でわかる意味、性質、試験、スランプ
- 混和材ってなに?1分でわかる混和材の目的と種類
- AE剤とは?1分でわかる意味、効果、添加量、減水剤との関係
- 細骨材率の基礎知識、すぐに分かる計算方法とスランプの関係
- スランプ試験ってなに?スランプコーンとスランプ値、Fcとの関係
- コンクリートのスランプ値は?1分でわかる意味と規定、スランプ値、18cm
- スランプフローとは?1分でわかる意味、スランプとの違い、測定方法、許容値
- コンクリートの空気量とは?1分でわかる規格、単位、許容値、計算式
- 水セメント比とは?1分でわかる定義、計算法、単位水量との関係
- 単位水量とは?1分でわかる意味、規準、水セメント比、コンクリートの種類との関係
▼カテゴリ一覧▼
- 鉄筋コンクリート造の用語を学ぶ(まずは、スランプ試験ってなに?スランプコーンとスランプ値、Fcとの関係から)
- 鉄筋と配筋の仕組み(まずは、鉄筋のサイズと呼び径の関係、必ずわかる鉄筋サイズの覚え方から)
- 鉄筋コンクリートの部材の計算(まずは、RCスラブのたわみから)
▼他の勉強がしたい方はこちら▼
更新情報
- 当サイトでは、ほぼ毎日、記事更新・追加を行っております。
- 更新情報として、先月分の新着記事を一覧表示しております。下記をご確認ください。
- 新着記事一覧
プロフィール

- 略歴▼
- 名前 ハナダユキヒロ/MITUME lab代表.
- 2010年 弊サイトを開設
- 2010~2017年 国立大学大学院修了
- 2017年12月に当HPが書籍化。
- 「わかる構造力学」
- 2022年4月に「わかる構造力学」の改訂版出版。
- 「わかる構造力学(改訂版)」
- 10数年以上、建築の学問、研究、構造設計の実務に携わった経験を元に、未経験の方、建築関係の学生、社会人の方に役立つ知識を、分かりやすくお伝えします。
- 当サイトの目的▼
- 建築学生が学ぶ「構造力学」の目的
- とりあえず10記事▼
- 初めましての方に10記事用意しました
- おすすめ書籍紹介▼
- ハナダユキヒロが建築関連書籍の良書を選びました
同じカテゴリの記事一覧
- 富配合とは?1分でわかる意味、読み方、貧配合との違い、杭との関係
- フレッシュコンクリートとは?1分でわかる意味、性質、試験、スランプ
- 混和材ってなに?1分でわかる混和材の目的と種類
- AE剤とは?1分でわかる意味、効果、添加量、減水剤との関係
- 細骨材率の基礎知識、すぐに分かる計算方法とスランプの関係
- スランプ試験ってなに?スランプコーンとスランプ値、Fcとの関係
- コンクリートのスランプ値は?1分でわかる意味と規定、スランプ値、18cm
- スランプフローとは?1分でわかる意味、スランプとの違い、測定方法、許容値
- コンクリートの空気量とは?1分でわかる規格、単位、許容値、計算式
- 水セメント比とは?1分でわかる定義、計算法、単位水量との関係
- 単位水量とは?1分でわかる意味、規準、水セメント比、コンクリートの種類との関係
- HOME > 鉄筋コンクリート造の基礎 > ワーカビリティとは?1分でわかる意味、スランプ、AE減水剤との関係
- 1級の過去問(計算)解説
- 限定メルマガ
- わかる建築構造の用語集・図解集
- 1頁10円!PDF版の学習記事